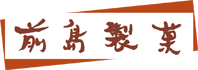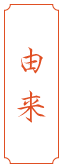九万五千石の由来
土浦城は室町時代末期の築城です。江戸時代には、松平氏や朽木氏が城を改築し、城下町や水戸街道を整備しました。街道沿いには商人、職人が移り住んで町家が並び、城下町土浦は、水戸街道の宿場、霞ケ浦水運の河岸として発展しました。寛文九年(一六六九)に入封した譜代大名土屋氏は、廃藩置県まで十一代が二百年にわたり土浦城を治めました。初代土屋数直は、幕府の老中として三代将軍徳川家光、四代家綱に仕え、二代政直は、五代将軍綱吉から八代吉宗まで四人の将軍に仕えました。三十年余りの老中在職中に政直は加増をうけ、土浦藩は九万五千石となり、常陸国で、水戸藩に次ぐ大藩になりました。 現在、亀城公園に残る櫓門や濠にかつての風情がしのばれます。 九万五千石の石は「イシ」とも読みます。菓子「九万五千石」は石垣の石をかたどり、質実剛健、風味高雅を特色としております。どうぞご賞味下さい。